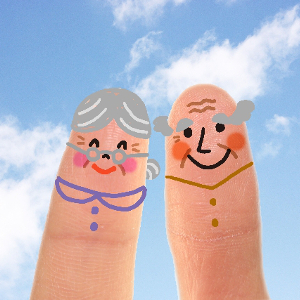要介護者がいる家庭においてはバリアフリー化は必須であり、そのために公的介護保険制度においては要支援・要介護の認定を受けた被保険者は支払基準限度額20万円を上限として、改修工事を行った場合従来通りですと一律その9割が償還されるという住宅改修の助成制度があります。
公的介護保険の住宅改修:要介護認定を受ければ利用できる
つまり1割の自己負担はかかりますが、20万円までなら改修にかかる費用については公的介護保険から助成金が出るということになります。また従来通りというのは2014年以前の制度においてのことであり、医療介護総合確保推進法が施行された2015年においては一定の所得以上の被保険者は8割の償還となります。
つまり法改正により自己負担が1割から2割に引き上げられました。住宅改修によるバリアフリー化は要介護者にとって必要不可欠なものではありますが、ではどういったものが住宅改修にあたるのでしょうか。ここでいう住宅改修とは主に以下のようなものが該当します。
① 廊下や階段、浴室などの手すり取り付け
② 段差解消のためのスロープ設置など
③ 滑り防止および移動円滑化
④ 引き戸等への扉取り替え
⑤ 様式便所の便器取り換え
以上のようにリフォームと比較すると比較的簡易的と思われる改修については、幾分か助成金があるという制度です。要介護認定を受けた方であればぜひとも利用したい制度ではありますが、次項のような課題もあります。
公的介護保険の住宅改修における課題:水増し請求など
では公的介護保険には住宅改修において助成があることは前述した通りですが、その課題について挙げたいと思います。まずよく言われるのが住宅改修の質が施工業者によっていくらかばらつきがあるということです。
当然公的介護保険制度上の問題ではありませんが、公的介護保険制度上においては、ケアマネージャーによる改修の理由書は必要となります。その場合、業者の選定については特に定められているものはありません。
つまり自分で工事をして、材料費を請求してもいいわけです。ここの業者に一定の基準を設けていないため、あらゆる業者もしくは業者まがいの者が施行を行うという事態により、改修の質のばらつきが生じているといいます。
または公的介護保険制度から助成金が出ることを伝え強引に施行を行い、割高な水増し請求をおこなっている業者もあるという問題もあります。すこし逸れましたが、介護のための改修費用は20万円ではまずもって不足しており、実際はもっと費用がかさむものです。
また自己負担が2割に増えたことから、家計の負担も増えました。現行制度の課題はまずこの介護にかかる初期費用の捻出には公的介護保険制度では不十分であるというところにあると思います。
初期費用対策:民間の介護保険でカバーすることも検討
介護にかかる初期費用=バリアフリー化、福祉用品購入等は平均で260万程度かかるといわれております。したがって本件の改修の助成や高額介護サービス費制度を利用したとしても相当な額の自己負担が強いられ家計が圧迫されるということは想像に難くありません。
公的介護年金制度のみでは到底カバーしきれないこの多額の初期費用については民間の介護保険をもって準備することが最も合理的で好ましいと思われます。
各保険会社の介護保険商品により差異はありますが、所定の要介護状態になった場合はまとまった一時金と毎年支払われる年金とが併給される保険も多いです。一度保険代理店等に資料請求を行い、民間の介護保険による備えも考慮しておくことをお勧めいたします。